大変なお題を選んでしまった…
これは本当に複雑で、測定値だけ見てわかるなら苦労はしないのだ。ただふんわりとした傾向はある。ふんわりと進めていきたい。
さて、アンプは大きく分けるとまずは真空管とトランジスター(D級も含めよう)に分けられる。それらも例えば真空管だと最近はむしろヨーロッパで流行りつつある純日本的な小出力なシングルアンプもあらば(四畳半趣味的な)大型送信管シングル、果てはKT150をクアッドパラレルにした化け物まで色々あります。
トランジスターやD級はあまりそんなバリエーションは無いですが、中にはfirstwattのようの珍妙な奴もありますな。
で、スピーカーですがオーディオ歴が浅いor希薄なオーディオ歴を歩んだ方はさもわかったような口振りでこう言います『能率が高いので真空管がいい』全然関係ないです。これが一番関係ない要素とすら言えます。
影響するファクターは複雑なので十把一絡げに言えません。ふんわりと話を進めましょう。
1.インピーダンス
当たり前ですが、最近はあまり此処等を語る人がとんと居ません。若手は意外と古いオーディオファイルより理屈っぽくない傾向があるようです。
インピーダンスと言ってもこれも幾つかのファクターがあります。例えば低いところが凄く低い低インピーダンスな物とか、或いは変動の大小ということもあります。
低インピーダンス代表はapogee Scintillaとか
公称1Ω、実測で1Ω台ですね。こんなスピーカーは現代にはありません。なおapogee acousticsもその後のスピーカーはインピーダンスがまともになり、3Ωとかに上がりました。良かったね。
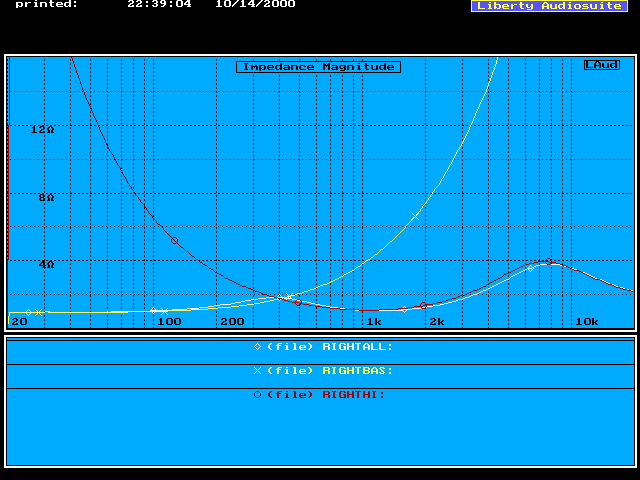
こう言う物は大型トランジスター、大電流だから…と言われ勝ちですがそんなことはありません。1Ωのスピーカーはあまり経験がないのでさておきまして、例えば3Ω程度なら『低インピーダンスは大出力トランジスターでないと鳴らせない』ということは全くの誤りです。むしろインピーダンス変動が激しいスピーカーの場合、安定する出力トランスがある真空管アンプの方が良いのです。真空管アンプはスピーカーの趣味がインピーダンスで出力が変わらないからだ。ただ激烈な電源と出力トランスを持ってれば、という条件付き。もっともダンピングファクターという問題でf特に変動がある。ただ、それは中域や低域が1dB程度持ち上がることになりむしろミュージカリティーとなりうる。え、巨大な真空管アンプは重くて辛い?それはそう。別にD級で良いです。
まとめると『インピーダンスでは形式に有利不利はない』です。トランジスターでも大出力アンプは基本的に大きいですし。
2.Q ファクター
Q、というとどちらかというと音楽製作者のほうが馴染みがありそうです。パラメトリックイコライザーとかでお馴染みのアレですよ。山の高さや鋭さ、と言えましょう。Qが低いとすぐ収束し、高いと特定周波数のピークが高く収束が遅くなります。
つまりQが低い方が制動が強く、高いと弱いわけですね。ただこれも低ければいいわけではなく、ある程度の範囲が良いとされています。0.6~0.8位ですかね。低いと制動が過ぎ低音が出なくなり、高いと制動が効かなさすぎこれもよろしくありません。
あまり難しく書きたくないので凄く大雑把な話にします。ユニット自体にまずQがあります。それをエンクロージャーに取り付けるとQが変化します。密閉だとスピーカーは大きくQが上がりますし(容積が小さいとなお上がる)、逆に平面バッフルとかだと全くQが上がりません。
そしてスピーカーユニットのQは主に磁力と振動板の重さで決まります。無論それだけではありませんが。概ね能率と相関するとも言えます。高能率だとQも低い。でも重い振動板や弱い磁力だと制動が弱くなるのはわかりやすいはずです。
ユニット自体がQが低い(つまり軽量ユニットでかつ磁力が強力)なものを最もQが上がらない平面バッフルに着けた日には恐ろしく低音が出ないカスのような音になります。
とは言え低音さえ何とかなるならQが低い方がハイスピードで素晴らしいのです。また今のスピーカーは基本的に高いQのスピーカーを高いDF(DFはアンプ側の制動力で、Q/DFのような相関になる)で動かす思想です。DFが低い(古典的回路の低出力真空管シングルとか)とそのような…密閉とかでかつ現代的な振動板が重いスピーカーだと制動が効かず悲しい音になります。
なお経験的には本質的な駆動力とDFは別物です。大規模な真空管アンプより遥かにDFが高いトランジスターでも、電源などの規模が小さいと駆動力は全く及びません。どうも電源の規模と駆動力は相関が大きいと思うんですよ、例外が無かったです。
逆にQが低いスピーカー…例えばALTEC 604(Qts0.2くらい)とかを平面バッフルなんてQの低さがヤバいですね…ただこれに先ほど糞味噌言ったような真空管シングルアンプがベストマッチだったりする。恐ろしく素晴らしい音がしたりします。またQが低い方がDFだけではなく駆動力、つまりは電源部の規模も小さくて済む傾向にあります。理屈やパラメーターで説明出来ませんが。
これで考えると『ある程度は』そのスピーカーに相応しいアンプが予想できます。例えば容積が小さい密閉の例えばYGとかは強力な制動のアンプが必要だし(ただ海外では大型真空管アンプで鳴らすことはかなり多い)、voxativeは先のALTEC+平面バッフルよりはバックロードホーンでQが高くなるのである程度の駆動力かつそんなに高くないDF…つまりは強力な電源部を持つ真空管アンプが有効です。先のALTECならに2Wのシングルアンプでブリブリに駆動できます。

山本音響工芸のスピーカー。まさにALTEC+平面バッフルだが、同社の駆動力皆無のシングルアンプ(持ってた)と合わせるとビックリするほど素敵な音がするのです。ネットワークもホーンも魔改造されてるので良い意味で全くALTECの音ではなく芳醇でクラシックが素晴らしい。
“スピーカーとアンプの向き不向き1” への12件のフィードバック
ダイソーのスピーカーで遊んでも良いと思いますよ。
4連直列1Ω以下普通のアンプ問題無く鳴ってますよ。🤣
また、カーオーディオのパイオニアのサブは効率的に1Ωぐらいで動かしてますね。
やっぱりそうですか
低インピーダンス自体は言われてるほどそんなに問題にはならないような気がするんですよね…
いつも参考にさせていただいてます(特にアナログ…リード線は効き目最高でした)。例えばQUAD ESLについては、向き不向きはどう判断すればいいでしょうか。よろしくご教授願います。
ご愛読いただきありがとうございます
QUADですが散々経験した限りだと『純正の組み合わせは駆動できてない』と言うことです。真空管アンプが合わない、というよりその後の何種類かのQuadのアンプでも聴きましたがそもそもトランスなどの物量が少ないのでダメです。
それなり以上の規模の真空管なら行けるかも知れませんが。
真空管で聴いている人は恐らくきちんとしたハイパワーアンプで聴いていないと思われます
なお良かったのは…意外でしょうが…アキュのAB級パワーでした。また良く出来たclassDアンプも素晴らしい相性です。
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
なんと…アキュですか??ノーマークでした。
これはD級でいってみようかと。
サウンドパーツpp(手持ちEL34/KT88特注品。現在パッシブスピーカー所有しておらず休眠中)でも駆動しきれないですよね。
いや、駆動出来ないとは言えないでしょうね…少なくともQuadの『小型真空管アンプ』に比べれば物量がまるで違います。Quadがパラヴィチーニに造らせたアンプも聴きましたがそれもだいぶトランスは小さいです
試す価値はあると思います
なるほど…QSL入手したら試してみます。
あESL…
原初のESLですか?それともシリーズのどれかでしょうか?
現時点では漠然と57を第1候補、63を第2候補に考えてます。他におススメなどありますでしょうか。壊れるのは覚悟の上でw検討中です。
返信遅くなりました
57の特徴は『最も素直だが指向性が狭いのでセッティングが難しいこと』と『二枚スタックじゃないとサブウーファーありでもキツイ』ことですね
63は完成形です
988、989と共に最もQuadのサウンドです
なお現行のは壊れにくい代わりに音がパツンパツンで良くない
修理に関しては、なぜかESLはドイツにファンが多く(グラモフォンなど多くのスタジオが採用していた)ドイツの人が製造機械の権利を買い取って作ってます。
なので新たなパネルはそこから買うことになるでしょう
確か日本でも取り扱ってるはず…
詳しく解説いただき、ありがとうございます。
アドバイスを踏まえて機種選定することにします。
併せてサブウーファーも検討したいと思います。